| 晴林雨読願望 take /草苅 健のホームページ   勇払原野のコナラ主体の雑木林。ここは中下層をウシコロシの黄色が占めている |
| 一燈照隅 雑木林だより 新里山からの日常発信 |
地域活動15年の歩みとこれから 勇払原野の風土を共有する |
| ●コンテンツ一覧 ●日々の迷想 2023 & 2024& 2025 2021 |
first upload: Nov. 29 , 1998 last upload: Jul 08 , 2025 |
| 日々の迷想 ■7/8 『庭とエスキース』を読んで 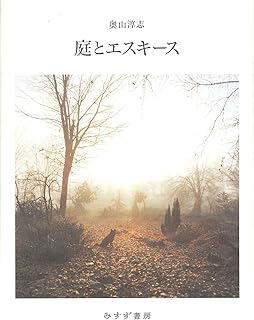 ちょっと不思議な、かつ、たいへん面白い、人情味と自然味が溢れる本を読んだ。場所は北海道の新十津川町の山あい、そこで繰り広げられるユーモアとペーソスが入り混じった自給自足の暮らしを、岩手の雫石に住む映像クリエーターのような若手写真家が15年近く四季折々に訪れ素顔と言葉を北海道弁そのままで描写していく。 ちょっと不思議な、かつ、たいへん面白い、人情味と自然味が溢れる本を読んだ。場所は北海道の新十津川町の山あい、そこで繰り広げられるユーモアとペーソスが入り混じった自給自足の暮らしを、岩手の雫石に住む映像クリエーターのような若手写真家が15年近く四季折々に訪れ素顔と言葉を北海道弁そのままで描写していく。井上弁造さんのゴミ屋敷のような小さな丸太小屋は、完成しないエスキースが主のアトリエになっている。庭は手放すと原野や荒れ地に戻るという開拓時代が匂う林と畑(いや、北海道は今でもどこでも昔に戻りたがっている)。そこで行われる営みに若いクリエーターは興味津々で向き合い、やがて北海道弁の年配者・弁造さんは亡くなる。 丁寧に北海道弁を切り取り、リアリティがあり、それらは機知にとんだ真理、アフォリズムと呼べるものに仕上がっている。例えば、ボンヤリをからかったら「年寄りからボンヤリをとったら何も残らん」「年寄りとはボンヤリ座っとる生き物だ」などと返す。「ユーモアはぺーソスを越える」など、意味深な言葉の数々を発見しつつたどる楽しみも多々ある。ある薪づくりのシーンでは、手伝ってもらった薪の山をみて「ああ、これでまた薪の暮らしを続けられるなあ」…。これはわたしの毎年の薪暮らしのシーンや感慨とも似る。 庭といい、人といい、そして薪といい、とにかく北海道に住み開拓や風景に関心を強く持つ者にとって共感するところが多い。だから並ぶように歩き、読んだ。ところでなぜ、若いクリエーターは、北海道弁で粗野な言葉づかいを隠さない老人のところに通い詰めたのか。老人の言葉に象徴されるアフォリズムは何を意味するのか。最後までしっかりした答えが見つからなかった。 だが読み終えて、わかった。人はきっと常によりよく生きるためのヒントを探して生きていくからだ。人の日常という足元には、メモを採りたくなるほどのアフォリズムが転がっていて、それらを丁寧に拾い集めている他者は、あるものにとってはヒントの山に見えるのである。ヒントは、抽象化し普遍化し磨いていくうちに音色良く響くようになるのだろう。聞く耳を持つものにのみに響く。まさに啐啄同時であろうか。 ■7/7 ワタリガニのみそ仕立てスープ  ブイヤベースのような魚のうまみ出汁は最も好きな料理のひとつだ。スーパーで石狩産のワタリガニ680円を見つけたのでさっそく一杯購入して、これだけで出汁をとり単純にうすいみそ仕立てにしてみた。多種混合したの複雑なブイヤベースとは違ってこれ一種のみ。しかし、いわゆるカニみそもにじみ出ていてそれに外子も付いていた。そのせいか、味付け前にすでに旨味がにじみ出ていた。食べるところなど、もとよりないに等しいワタリガニだが、鍋にせずそれだけで煮たのは正解だった。本当に美味しい魚の出汁は、体が喜ぶのがわかる。 ■7/6 今年は花の立ち上がりが早い    今年、ハンギングやコンテナに花苗を植えたのは5/26、ベランダで養生後、表に出したのは6/15、誇り始めたと感じたのは6/末、ちょっと誇るペースが前倒しの感じだ。6月の後半には時々摂氏30度近くなるのだから当然かもしれない。右下の写真奥のレンギョウも深みがあり、シュートの伸びも元気で、今朝早々に2回目の剪定をしたばかり。これから8月9月と肥料を切らさないで育て、旅行に出かけ始める秋の10月上旬ころには店じまいする。薪と花の相乗関係は今年もいいように思う。今日も暑く湿度の高い日だったが、予定通りレンギョウの2回目の剪定をして、草取りをし、物置の戸の不具合をカンナで削り無事修正して(この達成感はなかなか)、コシアブラの焚き付けを割った。林と花、混然一体となった仕事だった。 ■7/4 歌にみる庶民の共感 35 人は結局生きるのはひとりだから基本は寂しいものだと思う。しかし、何かにつけ他者との共感があったり声をかけられたりすれば、新たな縁が生れ別の世界が見えて元気をもらうことも少なくない。やはり人生は不思議に面白い。 ◎相席の見知らぬ人に声をかけ会話始まる伊勢参りのたび 新潟市・Fさん …旅先では声をかけやすく、また、かけられやすい。ましてや行き先が同じならば尚更。情報も仕入れたいし、あるいは教えて教えられて得する情報もある。さらにお互いの出身地などへたいていは話が弾む。想像するだけで楽しい。 ◎右へいせひだりかうやのしるべ立つ大和街道に夕暮れがくる 和歌山県・Sさん …伊勢や高野山の岐路に立ったようだ。いずれも憧れの地であったろう。大和街道は古えへの入口だ。まさに目に浮かぶ光景。伊勢にはできれば毎年参拝したい。高野山はもう一度行きたい。交通手段は発達しているから、今や意外と気持ちひとつ。 ◎雨風の音に目覚めて外見れば咲きし牡丹に傘立てる夫 山梨県・Kさん …暗いうちに思いやりあるこころに、相方は胸を熱くしたのではないか。絵になる図であり心象風景として忘れがたいし、ふとわが身にもそんなしぐさがあったような気がする。満開の牡丹は雨の重さで垂れんとしている。 ◎集落に郵便ポストが無き故に町営バスにて赴く暮らし 岡山県・Fさん …日本各地でこのような不便が日常化してきた。たしかに、高齢化してくる時代に難儀だが、割り切るしかない。毎日出すわけではないのだし、人は便利さに麻痺する。地方路線の廃止は最たる選択だった。全国の路線を税金で賄う選択もあった。しかし…。 ◎学校でマッチの擦り方習ひしと小五の孫が線香供ふ 藤枝市・Kさん …すごくいい話。じいちゃん、ばあちゃんに大事に育てられたのがわかる。先祖を敬う姿勢はなかなか受け継がれなかった。結果、家族の崩壊に向かうという識者もいる。先祖や歴史という縦の関係がないと、人間は横並びの競争に右往左往する。 ◎神社へと深々下げるその姿勢二十歳の孫よ善き人であれ 東京都・Jさん …このお孫さんもジジババからみれば誇らしいではないか。わたしは祖父母に育てられた経験がないが、神社ではせめてと上半身は神主さんのように直角に折る。実にせめてもの思いで、だ。 ◎けんめいに生きれば未来は明るいと占ひ師いふ八十四の吾に 城陽市・Aさん …占い師は顔を見るのを忘れたか、はたまたマニュアル通りか。しかし、額面通りに受け取ってもOKだ。生きている間は「懸命」に生きねばならないのだし、そうすれば死ぬまで明るい、と思い込むことも可能に、…なるかどうかは不明。 ■7/2 群落コントロールとフタリシズカ  静川の小屋周りでは、かねてからオシダとフタリシズカを刈り残し近年ではさらにスドキを移植し種を播くようにして群落を増やす方針を立てた。やったことはわずかだったにも拘らず、フタリシズカは一面の群落に育ち、スドキは拡散して放置しても増えるようになった。フタリシズカという名前は能楽の静御前にルーツがあると聞くが、ふたつの花のうちの一つは御前の亡霊ではなかったか。この暑いさなかでも、わたしは怪談は本当に怖くて遠慮したいが、この秋は足立美術館に向かう際は、怪談ものの大御所、小泉八雲の記念館と鉄の歴史を探る和鋼博物館に是非寄りたいと思う。 ■6/30 山菜や果実を通じて土地を知る   一昨昨日、裏山で家人と恒例の山椒を採った。もぐ都度に山椒の香りがただよって、セージやタイムなどハーブをいじっているときのような清涼感、もっと言えば健康感覚のようなものが漂う。採れたうちの3分の一は山椒が大好きな娘のもとにさっそく家人が郵便で送った。 そして翌日はジュンサイ。沼で採った少量を二人で分けていただいた。昨日はコモンズ研究の先生らとハスカップ採り。原野の採取はあきらめて、懇意にする農家で1.5kgを摘んだ。 季節の恵み、山菜とよく言われるが、わたしはいつも「土地の氣」をいただいたつもりでいる。「氣」は加齢とともに目減りしていくらしいというのを体が実感しているせいもある。またそうして、季節を巡る繰り返しで歳を重ねていくリズムができているように思う。土地のものにこだわらず、ホヤ、カニ、時シラズなど、俳句の季語を扱うように口に入れたい。上の二つをいただくといよいよ夏も本番になる。と思うかたわらで、スーパーにはわたしの大好きな桃が出てきたという。これは土地のものでは当然ないが、昔、桃生産をしていた実家を思い出す。季節の巡はいかにも早い。 ■6/28 ジュンサイ採り  山菜採りと称してジュンサイを採る人は稀だ。ボートの持ち主と出会い半日ほど借り受けることにしたので、朝から船に乗る。30分余りで予定分を採り終え、小屋の薪割り。春から初夏へ。衣替えのように忙しい。 ■6/26 歌にみる庶民の共感 34 調べものの多くはネット検索が多くなったが、漢字の読みなどは漢和辞典が欠かせない。わたしにとって、今でも知らない言葉が出てくるもっとも大きなジャンルは俳句ではないだろうか。季語や古語、よくもまあこんな漢字を使うものだなと感心することしばしば。それで、最近になって辻桃子編『実用俳句歳時記』を開く。今回は俳句にしぼって。 ◎桜蕊降り先生も綽名つく 葛城市 Nさん …どこか、漱石の『坊ちゃん』を連想させた。腕白な中高生あたりが、ひそひそと呼び合うのである。それも新学期始まってひと月ほどして。 ◎雨上がり雀隠れの匂い立つ 和歌山市 Hさん …スズメが隠れる草が目に浮かぶ。こういう観察を絶え間なくしていれば老いなど遠のくのではないか。「雀隠れ」という表現は初めて知った。俳句の世界は、観察、命名、季語が実に多様で深い。 ◎世のことは思案に余り花は葉に 神奈川県 Nさん …実に思案に余ることばかり。かつてこんなに情報に囲まれた時代はあっただろうか。しかも、生活に不可欠の情報かと言えば、疑わしいものも多々。SNSもそうやって突き放してみると、なくてもいい話ばかり、そして時には嘘だったり。俳句でもひねっている方がよほど生産的。 ◎あいそなき顔をそろえて溝浚え 富山市 Fさん …これなら川柳みたいに笑わせる。最近は近所だからと言って愛想笑いも世間話もないのかも。それはそれで楽なのだが、気持ちひとつ。どちらかと言えば、一言二言はかわせばぐんと変わるのに。 ◎森凉し一樹一樹の風の楽 香川県 Fさん …木々をくぐってやってくる風に個性が生れるような、そんな表現だ。風は音もある。それが涼風であったりすれば、天然のクーラー。 ■6/24 薪の館、発見して真似してみた  家人が2,3km隣の町内で「薪がたくさん積んである、うちと似たようなお宅があった」、というのでなんとなく見当を付けていってみた。なるほど、狭い敷地に息苦しいくらいに薪が積んであり、普通の一軒家では1年で使い切れない量だ。拙宅よりちゃんとして見えるのは市販の薪スタンドあるいはログラックというものを使っていて、一列の薪小屋にも木造りで屋根がかかっている、そしてそれはDIYのようでもある。 それではちょっと拙宅もログラックなるものを使ってみようかと、早速ネットで注文した。長さが2.4mくらいで高さ1.3m、幅は35cm、これを少し斜めにして道路側に寄せた。ベランダとの間に2mほどスペースが出来て動線が生れて、かつ、後ろにバケツや庭道具、自転車などが隠れる。それと地面と薪が接することがないので乾燥にはいいようだ。これでなんとなく、気分が一新。花も飾り始めたので、朝晩、ほうきで掃くのが楽しくなった。 ■6/22 やっと見えた明治維新の実像 昨朝、「翔ぶが如く」全7巻を読み終えた。今朝、雨降りしきる明け方に著者司馬遼太郎のあとがきを読んで茫然として時間を過ごす。茫然の訳はこの半年の間、暇を見つけて10pから20pというノルマを課して体力勝負のような読書をしてきたせいだ。それと維新という言う意味がようやくうすぼんやりからややはっきりと見えた安心、それと終了の安らぎのせいもあった。歴史を知らない70男が中でも興味が高かったのが幕末から明治維新とその後のあたりだった。この作品によって激動と表現される舞台裏を垣間見ることができたが、しかし、どうも言葉に尽くせない。示されたスペクタクルがあまりに大きい。茫然の理由はそこにもある。 司馬氏が15年来考え続け4年数か月で書き上げたというこのシリーズは、明治維新のあたりから明治10年の西南の役と呼ばれるエンディングまでを、西郷隆盛という実像のぼんやりしたヒーローと、近代日本の骨組みを実務した大久保利通を軸にして描かれているが、そこに薩長土肥の立役者とその配下、朋輩のエピソードが細々と拾い上げられ、時間と人を行ったり来たりする。記述の繊細さは、まるで著者自身のメモではないかと見まがうほどで、読むわたしの方はとても覚えきれない複雑さと量である。追いつけない迷路のような混沌に付き合わされる訳だが、わたしはフォローするのをすぐにやめた。また後半の6巻と7巻は中南九州一帯に展開された戦況を、地名や地形を丁寧に描写しながら克明に記述されるが、これも字面を追うだけで理解はできなかったし、読むのが苦痛だった だが明治維新というのが、武家社会だった日本が西欧標準に近づくにわか仕込みのリストラだったという実像は、これでもかというくらいに浮かび上がった。廃藩置県、廃刀令、地租改正、士族の消滅など、国の土台となる制度を根底から崩す荒療治を、たまさか維新前後に関わって勝者となった役者たちの、かなり恣意的なやりくりで進んでしまった。それほどの急ごしらえだった。ひずみは不満を募らせ、そのエネルギーは各地に貯まった。暗殺や反乱ののろしが挙がるのは当然だった。が、日本は欧米列強に近づく近代化の必要もあった。 司馬氏はあとがきで、日本の今を治めている官の機構は、所詮、「太政官政治」であること、それと同時に、関心を深く持って見つめているのは「土地問題である」と書いている。令和7年のこの激動と国民の不安も、そんな明治とその延長にあるととらえると、これまで遠くの時代と眺めていた明治維新とその後が、多少だがつながりを持って見えてくる。2段組、9ポほどの小さな活字、約330pの7巻という体力を使った本読みのおかげで得難い収穫が残った。2025年の記念すべき読書時間だった。 |
2025の6/19以前 は → こちら